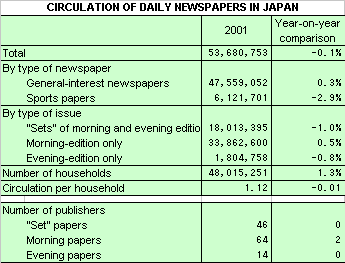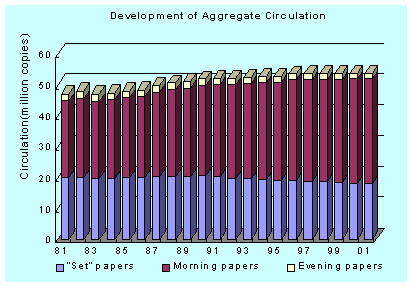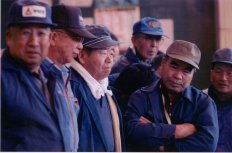|
NSK ニュースブレチン オンライン -------------------------------------------------------------------
<関連するデータは以下からリンクされています> 日本新聞協会は編集委員会(新聞、通信社など58社の編集局長、報道局長で構成)は、12月6日「集団的過熱取材(メディアスクラム)」について、取材者が守るべきガイドラインラインなどまとめた「見解」を発表した。 事件や事故の当事者、関係者に多数のメディアが殺到し、社会生活を妨げたり、プライバシーを不当に侵害するメディアスクラムについては、かねて批判があった。 新聞協会は「メディアがこの問題を樹種的に解決していくことが、報道の自由を守り、国民の知る権利にこたえることにつながる」とし、放送、雑誌などにも働きかける。 「見解」では、すべての取材者が最低限守るべきルールとして、?嫌がる当事者や関係者を集団で強引に包囲した状態で取材しない?通夜や葬儀、遺体搬送の取材では遺族らの心情を踏みにじらない?住宅街や学校、病院などの取材では静寂を阻害しない――などを挙げている。 一方、民間放送連盟も12月20日、集団的過熱取材による被害防止や問題解決のため、新聞協会とも連携を図ることなどを骨子とする留意点と対応策をまとめた。
米中枢同時テロの影響で日程を再調整していた新聞協会の2001年度日米記者交流計画の概要が決まった。同計画は新聞協会と米国ワシントンにある記者研修組織ICFJ(International Center for Journalists)との協力プロジェクト。双方の記者は2月の13日から17日間の日程相手国を訪れる。日本側の参加記者はワシントン、ニューヨーク、アトランタ、シアトルなどを訪問、ワシントンポスト外務部次長とのテロ取材に関する討論、国連やCNN訪問などを予定している。 米国からの参加記者は、日本の有力政治家や財界人、外務省、NTTドコモなどを取材、日程後半には沖縄を訪問、米軍基地や地元新聞社を訪れる予定。2月27日にはハワイの東西センターで双方の記者が合流し、総括討議を行う。 Topics.......Topics.......Topics........
|
 波乱の幕開けとなった新世紀。米同時多発テロは世界中に最大級の衝撃を与え、一方で深刻な経済不況の危機を招来した。日本にあっても外交・安全保障の新たな局面に入り、経済環境も猶予ならない事態にたちいたっている。この時代環境にあって、新聞の役割はますます重大である。
波乱の幕開けとなった新世紀。米同時多発テロは世界中に最大級の衝撃を与え、一方で深刻な経済不況の危機を招来した。日本にあっても外交・安全保障の新たな局面に入り、経済環境も猶予ならない事態にたちいたっている。この時代環境にあって、新聞の役割はますます重大である。