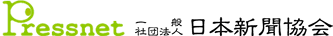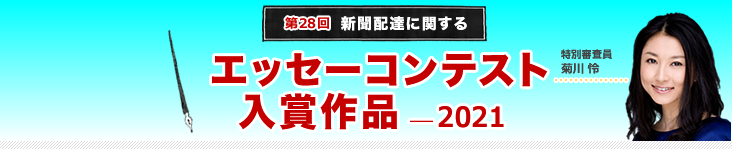最優秀賞
エール

「街灯を頼りに」
南日本新聞社
大学受験も間近に迫り、気持ちに余裕がなくなりかけて迎えた2021年の元日。その朝のポストには、朝刊と1通のお手紙が入っていた。「いつも新聞を購読いただきありがとうございます。先日は、大変うれしかったです。今年はあなたにとって最良の年でありますように」と。
きっかけは昨年のクリスマス。気分転換のつもりで真夜中外に出ると、吹雪。この雪ではサンタさんのみならず、新聞配達員さんも朝刊を届けるのは大変だろうと、雪かきをしてポストまで細い道をつけた。そしてクリスマスだったことを思い出し、板チョコにいつもありがとうのメッセージを添えポストに貼り付けた。翌日、お手紙はなくなっていた。
そして元日の朝、わざわざお返事をいただけたのだ。中にはお守りが二つ。それを手にすると、見守り、応援してくれる人がいる幸せを感じ、心が熱くなり涙があふれた。
新聞配達員さん! いただいたお守りを握りしめて受験した大学には無事合格。春から東京で一人暮らしを始めました。お守り大切にしますね!

「街灯を頼りに」
(南日本新聞社)
審査員特別賞
心に届いた 思いやり
当時の私は、とにかく寝不足だった。初めての子育て。3時間おきの授乳。抱いて子守歌を歌ってやっと寝かせつけたのに、布団へ寝かせようとすると途端に目を覚まして大声で泣く始末。だから私は、抱っこしている腕を揺らしながら着陸モードに入らなければならない。背中を布団に置き、抱き続けて汗ばんだ手を慎重にほどき、そして完全に寝るまで、体を優しくトントンとさするのだ。
アパートの郵便受けは壊れて受け皿がなかった。玄関ドアの口から入れられた郵便物はドサッと音を立て、たたきに落ちる。だがいつからか、新聞だけはたたきに落ちずに郵便受けの口に挟まれているのだ。授乳で起きた私は新聞が届くのを待った。午前4時。その時が来て私はドアを開けて配達員へ尋ねた。
「赤ちゃんが物音で起きないように」
あぁ。うれしかった。分かってくれている人がいた。空腹を満たして私の腕の中で眠っているわが子に頬を寄せ、甘い香りを嗅いだ。
優秀賞
あの子を忘れない
その日は曇り日だったが、いつものようにバイク後部荷台に夕刊を積んで出発した。
順序よく配達し、つぎは4階建てのアパートだ。
15部を持って配達先へ向かおうとしたら、目に見えない程の細かい雨を腕に感じた。いつも持参するビニールを荷台にかぶせ配達を始める。急ぎ足でも7、8分はかかる配達を済ませ階段をおりてきた。
急いでバイクに戻ってみると、荷台のそばにランドセルを背負った女の子が傘を差して立っていた。傘は荷台に広げられている。学校帰りの見知らぬその子は私が配達を終えるまで、雨にぬらすまいと新聞を守ってくれていた。
絹のような小雨だったが、荷台の軽い装備が気になったのだろう。高学年らしいその子は照れるような笑みを浮かべ、傘をすぼめた。
こころ優しい行いがとてもうれしくて、感動している気持ちを大きく表現したかったのだが、ありきたりの言葉しか思い浮かばず、はがゆい思いをしたことを思い出す。
あれから20年がたつ。
入選(7編)
少年からもらった「覚悟」

「暗闇の中、新聞を積んでさぁ出発です」
(京都新聞社)
雪の朝、除雪のためいつもより早く外に出た。新聞受けの新聞と雪の中の足跡が目についた。「たいへんだ」と思いながらスコップを取った。
母は89歳になる。父の他界後の30年余を独りで生きてきたが、思うように体が動かなくなり、そのうえ認知症を患った。介護しながらの仕事には限界がきた。母の住み慣れた家でともに暮らすことにした。3か月が過ぎた頃、予想以上に厳しい現実と先の見えない不安で、私のいらいらが募り、母への言動が厳しくなった。そして、後悔で眠れぬ夜を繰り返した。
翌日も大雪だった。くさくさした気持ちで除雪をしていると、「おはようございます」という少年の声。「君が新聞を配っているの」と問う。「お母さんは風邪だし、おばあちゃんは施設に行ったので……」と言う。登校前にもかかわらず、こんな小さな少年が家族を助けている、と思うと胸が熱くなった。
あれから4年。居眠りする母を前に、あの少年はどうしているかなあと思う。彼のおかげで私の覚悟ができたのだという感謝とともに。

「暗闇の中、新聞を積んでさぁ出発です」
(京都新聞社)
あの日の音とともに

「読者一軒一軒の新聞受けに丁寧に配達するスタッフ」
(山形新聞社)
―カタン。
一瞬耳を疑った。だが、間違うはずもない。幼い頃から幾度となく聞いてきた、あれは郵便受けの音だ。まさかと思ったが、新聞が届いたのだ。
母と夫と3人、実家の狭い茶の間に身を寄せ合うようにして寝ていた。とにかく情報が欲しかった。分かったのは、尋常でない地震が起きたということだけ。テレビも携帯も、電気が使えなくなった途端、無用の長物と化した。文明の利器がこんなにも脆弱(ぜいじゃく)なものだったとは。
「いつ電気がつくの?」「外は何がどうなっているの?」
真っ暗な中、寒さに拍車をかけるように湧きおこる疑問と不安。そんな時だった。新聞が届いたのは。
たった2枚8面の薄い新聞だった。だが、そこには平時の何倍も厚い思いが込められていたと思う。あの非常事態でも、いや、非常事態だからこそ、絶対に情報を届けようという作り手の思い。新聞に触れたとき、人の温かみと力強さを確かにそこに感じた。
あれから10年。今も「カタン」という音が、耳の奥で鳴っている。

「読者一軒一軒の新聞受けに丁寧に配達するスタッフ」
(山形新聞社)
浪人生活

「1日の作業は綿密な作業確認から」
(産経新聞社)
大学受験に失敗したので1年浪人することになった。予備校通いだけの毎日ではダメだという父の言い分を受け、1年間、新聞配達のアルバイトをした。1年後、受験に合格し、大学に入ることになった。
「一つ年下の人と同級生になるんだな」
なんとなく劣等感めいたものを感じ、そんなことをつぶやいたら、父が言った。
「お前は1年間、自分の脚で稼いだんだ。もっと自信を持て」
私は1年間、自転車で配達をしていた。今から30年近く前のこととはいえ、すでにバイクでの配達が主流であり、自転車は珍しかった。
「朝、暗いうちから起きて、重い新聞を満載して自転車で配達するのは並大抵のことではない。胸を張って大学に行け」
いつもは厳しい父が、自転車での配達を評価してくれたことが、とてもうれしかった。

「1日の作業は綿密な作業確認から」
(産経新聞社)
新聞配達で救える「命」実感

「膝まで埋まる雪の中、新聞配達に向うスタッフ」
(新潟日報社)
新聞配達を始めて10年余、大雨に見舞われた昨年の7月末の早朝、いつものように12世帯のアパートに配達をしたときでした。
一人で暮らしている80代の男性高齢者のドアの前で異変を感じ、立ち止まりました。
前日の新聞が取り込まれていない状態だったので、ドアをノック。応答がないので新聞を押し込み、ドアの隙間から部屋をのぞきびっくり。
布団の上に倒れたまま起き上がれない様子を見て、大きな声で「大丈夫ですか?」と呼びかけました。手を動かしながら「大丈夫」と応答したのでホッとし、とりあえず、包括支援センターに連絡、救急車を手配して市立病院へ搬送、一命を取り止めました。
翌日、親戚の方から入院して点滴を受け、食欲も出て元気になりましたとの電話をいただき、新聞配達が、大切な「命」を救う見守りにつながっていることを実感した出来事でした。
高齢者の孤独死をなくすためにも、新聞配達員の果たす役割がより大切な時代だと痛感しました。

「膝まで埋まる雪の中、新聞配達に向うスタッフ」
(新潟日報社)
新聞配りのシゲちゃん

「田園風景の中を配達する様子」
(朝日新聞社)
凍った朝の空気を震わせて、1台のバイクがかけ上がってくる。
新聞配達人は、今年67歳の同級生のシゲちゃんだ。シゲちゃんは目玉が大きくて漫才の西川きよしさんによく似ている。
私たちが中学生の頃、グループサウンズが大人気で、「わしらもテレビに出るぞ」と応募ハガキを何枚も出して、下手なギターをかき鳴らした仲間のひとりだ。
そのシゲちゃんは、3年前の7月、山崩れや洪水で町じゅうが全滅したあの日も、顔まで泥だらけにして、昼の3時ごろ新聞を届けてくれた。この前の朝、久しぶりに話をした。
シゲちゃんのお母さんが亡くなった。コロナ禍で面会もできず、寂しい別れをしたようだ。葬式の日の朝も新聞を配ったシゲちゃんは、自分を親不孝者だと嘆くので、「それは違う、シゲちゃんエライぞ」と肩を揺すぶってやった。シゲちゃんは、ありがとうと言って、泣きそうな笑顔を見せて、また来た道をバイクで走っていった。

「田園風景の中を配達する様子」
(朝日新聞社)
あの日、新聞は届いていた

「駅前で号外を配布」
(徳島新聞社)
ハアハアハアハアハア……
エレベーターの陰から聞こえてきた荒い息遣い。その時、どうしてすぐに気がつかなかったのだろう。それが新聞配達員さんの声も発せないほどのものであったと。
2018年9月6日。北海道全域を襲った胆振東部地震。突然のブラックアウト。テレビも携帯もダメで、小さなラジオと懐中電灯で不安な夜を過ごした。一体何が起こったのか……。翌日、外の様子を見ようとドアを開けて驚いた。届いているのだ、新聞が!マンションの11階、エレベーターも止まったままの我が家に。
そう、あの息遣いは、そうだったのだ。
停電下でも確かな情報を届けようと取材、紙面作り、印刷、配送、販売店、そして配達員、新聞制作にかかわる全ての方々の使命感を感じ、思わず目に涙があふれるのを感じながら、むさぼるように紙面を読んだ。
あの日から3年。新聞は今日も玄関に届いている。

「駅前で号外を配布」
(徳島新聞社)
新聞のもつ温もり

「若者とベテランで」
(信濃毎日新聞社)
我が家の隣は、40代の夫婦が営む新聞販売所だった。早朝3時には電灯がつき、次々と配達員の自転車が集まってくる。私は「人手が足りないの」と言われ、少しの間配達を手伝ったことがある。その中に小柄な中学生の男の子がいた。受け持ちの新聞を後ろ荷台にしばり、残りを前かごに入れると、毎回店の中に向かって手を振る。すると、店の奥さんが走ってきて握手する。そして肩をポンポンとたたくと彼は出発する。いつだったか、奥さんにその朝の儀式の訳を聞いた。彼は父親と二人暮らし。父親は、母親の温かさが足りないのがかわいそうだと話した。奥さんは「なら私の体温でも役にたてばと思い、毎日握手で送り出しているの。触れ合ううちに、我が子のように思えてきたわ」と笑った。
昨今、テレビやネットより遅い情報である新聞を、こんなに心待ちするのはなぜだろう。やはり、人の手で配達される新聞が、情報だけでない目に見えない魅力を発しているのかもしれない。天候、気候など関係なく届けてくれるそのありがたさ、配達の子の温もり、送り出してくれる販売所の人の温もり、新聞という紙の温もり――温もりが2倍、3倍になって、私たちのもとに届いているに違いないと思う。

「若者とベテランで」
(信濃毎日新聞社)
最優秀賞
思い出を胸に抱いて

「走る~今日も待ってくれる人がいるから」
(北海道新聞社)
フリージア、かすみ草、スイートピー……。我が家に漂う新聞のインクと花の香りには、ある中学時代の出来事が隠されている。
それは意識をなくして倒れた下校途中のこと。優しい新聞配達員の方に私は助けられた。当日、名前を聞かずに別れた配達員さん。お礼をどう伝えるか家族と悩んだ末に、「ありがとうの気持ちやね」が口癖の祖母の案を実行した。感謝の旨を記したメモに庭で育てた花を添えてポストの所に貼るというものである。新聞で花言葉の広告があるのを見つけてからはそれを参考に花を選んで、何十日も直接会うことを願い、待ち続けた。そのかいあって、ついに会える機会が設けられた矢先にご病気で亡くなったと知らせが届いたのだった。そうして、読み終わった新聞のそばに花を飾るようになった。命を救ってくれた恩人に深い感謝と追悼の意を込めて。
私はこの思い出を胸に抱いて生きている。配達員さんの親切を忘れないと誓いながら。

「走る~今日も待ってくれる人がいるから」
(北海道新聞社)
審査員特別賞
私、新聞配達始めたの
「私、新聞配達始めたの」。笑顔でこう言ったのは、私の友人だ。私は、自分の耳を疑った。あんなに朝に弱く、いつも寝坊するような人が新聞配達をできるのだろうか。
「朝、起きられるの」と私は友人に尋ねると、「そう。最近、早起きできるようになったの。それでね……」とうれしそうに話し始めた。どうやら、新聞配達を始めてから、良いことがたくさんあったそうなのだ。朝の空気は少し冷たく、ヒヤッとして気持ち良いらしい。そして、人が少ないから貸し切り状態だとか、配達先の寝ている犬の姿がかわいいとか、息つく間もなく語っている。疲れないのか私が尋ねると、「もちろん疲れるけど、楽しい」。曇りない笑顔で言った。私の友人は、新聞配達で変わった。新聞配達は、疲れるし、早起きしないといけないし、嫌なことがたくさんだと思っていた。これは間違っていた。新聞配達で人は変わる。友人が変わったように私も。次は私が言う。
「私、新聞配達始めたの」
優秀賞
感謝のこころ
家の近くの新聞販売店の前を通るたび、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」の活版所を思い出します。店の横に視線が行くのは、アルバイトのジョバンニを探しているのではなく、配達員さんのバイクが隙間なく整然と並べられ、ハンドルの向きもそろっているさまが美しいからです。そのバイクが、一台一台とあっという間に視界から消えていきます……。夕方、配達員さんが足早に集まってくると、店の軒下のツバメの巣の中が騒がしくなります。新聞を抱え店から出てくる配達員さんたちが、道行く人に会釈しながら、バイクで走っていく姿を5羽のヒナも巣から顔をのぞかせ鳴きながら見送っています。新聞配達の世界大会があれば、知ってほしい日本の美しい光景です。
子どもの日、かぶとを作ってもらった新聞紙。上から読んでも下から読んでも「しんぶんし」。祖母から教わったその音の響きも紙の柔らかさも好きです。ニュースを紙で届けてくれる新聞配達の皆さん、ありがとうございます。
入選(7編)
新聞配達員について

「バイクに新聞を満載し配達に出発する従業員」
(上毛新聞社)
僕の父は新聞配達をしている。正直、今時新聞を読む人なんてほぼいないだろうと思っていた。
ある日、夜中に目が覚めてしまい、その日は休みで暇だったので父の仕事についていってみた。そこで、新聞配達のイメージが変わった。僕のイメージは、誰とも会わずに黙々と配達しているような感じだったが、実際は散歩中の方や、家の前で配達を待っている方と楽しそうに話しながら配達をしていた。それを見て、新聞がまだ多くの人に必要とされていることや、新聞配達員がみんなに愛されているのを知ることができた。
新聞は、朝早くから配達してくれている新聞配達員の方や、それを待ってくれていて、毎日あいさつや感謝の言葉をくれる地域の方など、さまざまな人の思いが結ばれたものだった。それに気づけたあの日から、新聞を読んでから登校するようになった。新聞配達のおかげで、さまざまなことを学ぶことができた。ぜひ経験してみてはどうだろうか。

「バイクに新聞を満載し配達に出発する従業員」
(上毛新聞社)
祖母の命を救ってくれた配達員さん

「暗闇の中、新聞を積んでさぁ出発です」
(京都新聞社)
「おばあちゃんが倒れた」。まだ2月の寒い朝、父からその話を聞いて驚いた。父によると、新聞配達の方が玄関先で倒れている祖母を見つけて、家の中へ運び、救急隊の方に連絡してくれたらしい。2月の朝はまだ暗く、玄関と郵便受けは距離があったため、もし新聞配達の方が気づいてくれていなければ……そう思うと怖くなる。幸い祖母は、その後入院したが、意識も戻った。コロナ禍もあり、面会もできずにいるが、周りの人と会話するなど元気ではいるそうだ。
新聞配達は、ただ新聞を配るだけでなく、一人暮らしの老人などのお宅は、異変がないか普段から気にかけて配達しているそうだ。配達だけでなく、社会貢献を意識しているのだ。とても素晴らしいことだと思う。
私はまだ、高校生で何かをする力はないが、これからボランティア活動などに積極的に参加し、私のできることで、周りの人の力になりたいと思った。

「暗闇の中、新聞を積んでさぁ出発です」
(京都新聞社)
夕刊のおばちゃんと出会って
マドン・ティリー(14歳) 高知市

「街灯を頼りに」
南日本新聞社
「あらっ、久しぶり~」
誰かなと思うと、あの思い出の夕刊のおばちゃん。約半年前に高知新聞の夕刊が休刊したため、最後の配達以来会えていませんでした。そんな中、思いがけずお会いできて懐かしい気持ちになりました。
私が引っ越してから7年の間、まだ夕刊を配達していた頃、毎日おばちゃんのバイクと明るい話し声が聞こえてきて、学校帰りの私ともよく最近のことなどについて楽しく話していました。日常の中でそんなほのぼのしたひとときが大好きでした。最後の配達の日に私が今までの感謝の手紙を書くと、ものすごく喜んでくれました。私にとっても悲しく残念なお別れでした。
でも、おばちゃんの笑顔や温かい心を忘れることはありません。日常の普通の場面の人とのつながりが特別な幸せをつくるということもおばちゃんから学びました。私は、夕刊のおばちゃんと出会えてよかったと思っています。本当に、ありがとうございました。

「街灯を頼りに」
南日本新聞社
母を笑顔にしてくれた配達員さん

「走る~今日も待ってくれる人がいるから」
(北海道新聞社)
一人暮らしの祖父の家は、海の見える高台にありました。玄関ドアから新聞ポストまでの長い外階段を、80歳を超えた祖父が手すりにしがみつくようにして、一段一段新聞を取りに行きます。心配した母は門に張り紙をしました。
「新聞配達の方へ。階段の上り降りが困難ですので、玄関ドアまで届けてくださると助かります」
翌朝、新聞はちゃんと階段上まで届いていました。その日の夕方、母は夕刊の配達を待ち構えていて、バイクに乗ったお兄さんに何回も何回もお礼を言いました。お兄さんはちょっと困ったような顔をして、母に粗品を手渡してくれました。新聞名が印刷された薄いまな板でした。祖父の家から帰る新幹線の中で、いつもは泣いてばかりいる母がニコニコしていたことをよく

「走る~今日も待ってくれる人がいるから」
(北海道新聞社)
自粛期間を通して

「早朝、マスク姿で配達に出発」
(中日新聞社)
毎朝6時に起き、母が作る朝食を待つ間に新聞を読む。私のモーニングルーティンだ。以前は新聞を開く時間帯がさまざまで、読むのもテレビ欄と漫画が中心だった。しかしコロナ禍の緊急事態宣言下でリモート授業となり、生活を自己管理する必要性が出てきた。少し早起きしてゆっくり新聞を読む時間を取るようにしてから、生活に彩りが生まれた。休日の朝は更に早起きをしてランニングもするようになった。まだ街灯と夜明けの太陽が同じ明るさの道を走りながら、授業で習った「東雲」という言葉が浮かんだ。リモート授業で先生が黒板に書いてくれた「朝」を表す言葉はたくさんあって画面からはみ出すほどだった。
そして今朝もあくびをかみしめるようにして玄関に向かうと、玄関ポストにはすでに朝刊が届いている。私の生活を規則正しくしてくれるこの新聞は、見えないところで多くの人の手で作られているんだなぁと思いをはせる。取材する人、記事を書く人、印刷をする人。リレーで言うならアンカーの新聞配達員さん。完走して私の手元に届き、私の彩りのある生活を支えてくれてありがとう。

「早朝、マスク姿で配達に出発」
(中日新聞社)
優しさのカイロ

「地域のつながり大事に」
(高知新聞社)
ある冬の寒い日。母が外出していることをすっかり忘れていた小学1年生の私は、家の鍵を持っておらず、玄関前で一人泣いていた。母の帰宅を待っていると、夕刊を届けにきた新聞配達員のおばさんが「どうしたの」と声をかけてくれた。事情を説明すると「おばちゃんカイロ持ってるからあげる」とカイロを差し出してくれた。今思えば、配達中に体を温めるために持っていたカイロだったのだろう。
その配達員さんはあの寒い日から7年がたった今も、私の家に新聞を届けてくれている。中学校に入っておばさんと会うことは減ってしまったが、会った時には大きくなったねと声をかけてくれ、見守ってくれていることを実感している。そして今も寒い日にはあの日を思い出す。私もおばさんのように人への優しさや思いやりを持ち続けたい。

「地域のつながり大事に」br> (高知新聞社)
祖母の話し相手

「毎朝笑顔で新聞を届けます」
(北國新聞社)
私の祖母はいつも新聞を読んでいる。祖母の姿を見かけるとたいがい新聞を読んでいるので、小学生の頃になぜそんなに新聞が好きなのか聞いたことがあった。「付き合いが長いから」。祖母は新聞を読みながらそう答えた。意味がわからなかった。付き合いが長いと新聞を好きになるのか。そんな疑問を子供心に抱いたのを覚えている。
高校生になった私は訳あって祖母の家に住むことになった。住んでみて気づいたのだが、祖母は新聞配達員の方と仲が良い。20年以上の付き合いらしく、よく玄関で談笑しているのを目にした。ある日、30分近く話をしている姿を見てふと、祖母と長話をしていて時間は大丈夫なのかと心配になり配達員の方に尋ねたことがあった。すると驚くべき答えが返ってきた。祖母の話の相手になるために、うちへの配達が最後になるように配達の順番を調節しているとのことだったのだ。祖母の新聞好きがわかった気がした。

「毎朝笑顔で新聞を届けます」
(北國新聞社)
最優秀賞
ポストに優しさ届いた

「ワンちゃん『おはよう』」
(琉球新報社)
「うお~。すごく新しい! どうしたと」
新しい郵便ポストを見つけて祖母に聞いた。学校から帰ると、手作りの郵便ポストがかけてあった。それは、新聞配達のおじちゃんが作ってくれたそうだ。母に聞いてみると、小さい頃に会ったことがあるそうだが覚えていない。私は、どんな人か会ってみたくなった。気になったものの、家に新聞が配達されるのは朝の4時。お礼を言いたいが早すぎて起きられず数年が過ぎた。新聞が届かない日は、おじちゃんが倒れたのかと心配になる。そして、休刊日と聞いてほっとする。
今年思い切って、祖母が育てた新たまねぎを持っておじちゃんに会いに行った。新聞配達を始めて40年。毎朝3時に起きて、50件配達するそうだ。どうしてそんな大変なことを40年も続けているのか聞いてみた。それは、読者に喜んでもらいたいから……。言葉にならなかった。80歳過ぎても、新聞だけではなく優しさも届けてくださっていると思い心から感謝した。

「ワンちゃん『おはよう』」
(琉球新報社)
審査員特別賞
雨粒が気付かせてくれたこと
「コトン」
来たっ。私は、急いでくつをはき、玄関のドアに走り寄った。新聞の配達員さんは、少し驚いたようだったが「おはようございます。早起きだね」とさわやかなあいさつと一緒に新聞を手渡してくれた。今日は、前に応募した読書感想文の入賞者が新聞で発表になる日だ。新聞が入った薄いビニールの袋を急いで破ると、私は新聞を広げ、一ページ一ページていねいにめくった。
「あった。あった」
新聞に載っていたのは私の名前だ。うれしくて飛び上がった。私は、ふと、新聞が冷たいことに気付いた。新聞が入っていたビニール袋の表面には、雨の粒がいっぱいついていた。新聞配達員さんが雨の降る寒い中、新聞を配達してくれていたことに、気付きはっとした。……ありがとう。私は、心の中でつぶやいて、新聞を胸に強く、だきしめた。
優秀賞
届けてくれてありがとう
1月、1メートルをこえる雪がつもった。
「ない、ない、新聞が届いてない」
父が言った。起きたらすぐに新聞を読むことがルーティンで、これをしないと一日うまくいかないらしい。近所に住む祖父にかく認してみると、やっぱり届いていない。それどころか、じょ雪車が田んぼにおっこちて、道がふさがり、だれも祖父宅に近づけないらしい。
「新聞が届かないなんて初めてだけど、配達員さんの命が一番大切だよね」と、ぼくは母と話していた。
でも次の日。雪の量は前日と変わらないのに、2日分の新聞が届いた。まだじょ雪車がうまっている祖父宅にも届いた。
新聞が毎日、ぶじに届くのは当たり前じゃない。配達員さんが安全に気をつけて、努力してくださるからなのだと、心から思った。
2日分の新聞を前のめりで読む父の姿がみられてうれしかった。配達員さん、ありがとう。これからも気をつけて、新聞を届けてください。
入選(7編)
まいにちまってるよ

「田園風景の中を配達する様子」
(朝日新聞社)
2019年12月8日のしんぶんに、わたしがかいたえがのりました。
しんぶんにのりたかったわたしに、おかあさんが、しんぶんのみんなでつくるコーナーをみせておしえてくれたので、はがきにえをかいてしんぶんしゃへおくりました。
のるかのらないかドキドキしながらまちました。そのときしんぶんがまいにちおうちにとどくってすごいなとおもいました。
だれがしんぶんをとどけているんだろう。わたしはしんぶんをはいたつしているひとをみたことありません。それはわたしよりずーっとはやくおきてはいたつのおしごとをしてくれてるからです。
しんぶんはいたつさん、わたしのかいたえがのったしんぶんをとどけてくれてありがとうございます。
これからもはいたつおねがいします。

「田園風景の中を配達する様子」
(朝日新聞社)
おじさんのおじぎ

「さあ配達だ」
(毎日新聞社)
しんぶんはいたつのおじさんはいつもおじぎしている。
くばってくれているのは夜中なのに夜にしゅう金にもきてくれる。その時もお金をもっていったらすごくていねいにおじぎをしてくれる。ぼくが、いつもありがとう、というとまたおじきしてくれる。大へんな仕事なのにおじぎまでしてくれる。
お姉ちゃんの絵がしんぶんにのった時はラミネートまでして記事を持ってきてくれて、また、おじぎしてくれた。ありがとう、はぼくたちなのにいつもおじぎでありがとうと言ってくれる。もう引っこしして会えないけれど、おじさんのおかげでぼくたちもしんぶん読んでいるよ。まだ読めない字もたくさんあるけれども、おじさんたちが一生けんめいはこんでくれているからちゃんと読みます。ありがとう。

「さあ配達だ」
(毎日新聞社)
おつかれさま計画

「膝まで埋まる雪の中、新聞配達に向うスタッフ」
(新潟日報社)
今年の冬は大雪で、私の住んでいる町にもたくさんの雪がふりました。
祖父と父が毎日雪かきをしても、おいつかないぐらい雪がふり続けました。私と兄は家族を助けたいので、雪かきのお手伝いをしました。まだ明るくなる前の朝から、がんばって雪かきのお手伝いをしました。
そんな雪をかきわけるように、新聞配達のおじさんが来ました。おじさんは雪かきをしている私と兄に、「おつかれさま」と声をかけてくれました。私ははずかしかったけれどとてもうれしい気持ちになりました。
私は大雪で車も上手に走れない中を、何十けんも新聞配達をするおじさんの方が、私よりも何倍もつかれるだろうなと思いました。
私は1日だけのお手伝いだけど、おじさんは毎日雨がふっても、雪がふっても配達していてすごいと思います。
私と兄は早起きをして、おじさんに「おつかれさまです」と言う計画を立てました。

「膝まで埋まる雪の中、新聞配達に向うスタッフ」
(新潟日報社)
とう明な「ありがとう」

「読者一軒一軒の新聞受けに丁寧に配達するスタッフ」
(山形新聞社)
「はい。新聞取ってきたよ」
ぼくの一日は、ポストから新聞を取ってくることからはじまる。
ある日、いつのものように新聞を取りに行くと、ポストに指のあとがついていることに気がついた。そうじをしていなかったからよごれがたまってしまい、配達員さんが新聞を入れるときについたものだった。ポストについた指のあとを見ていたら、毎日一番早く「おはよう」を届けてくれているのに、ごめんなさいと思った。
お母さんからぞうきんをかりてポストをピカピカにしてあげると、「毎日おはようをありがとう」というぼくの気持ちを表してくれているようだった。本当は直せつお礼を言うのが一番だけど、それはなかなかできないから、これからはピカピカのポストで感しゃの気持ちを伝えられたらいいな。
配達員さん、ぼくのとう明な「ありがとう」届いていますか?

「読者一軒一軒の新聞受けに丁寧に配達するスタッフ」
(山形新聞社)
おはよう

「暗闇の中、新聞を積んでさぁ出発です」
(京都新聞社)
「あれ?」
いつもより早おきした日。新聞がまだきていない。少したって、もう一ど見にいく。ちょうど、はいたつのお兄さんが新聞を入れようとしているところだった。
「おはようございます」
門の内がわから、こえをかける。
「わ、びっくりした! おはよう!」と言いながら、お兄さんは新聞を手わたしてくれた。
2年生になって、自分用の新聞を読みはじめた。新聞は、日本中、せかい中のことを教えてくれる。この日わたしはまた一つ、新しいことをしった。新聞は、とどけてくれる人がかならずいるということを。ありがとうと言われなくても、はいたついんの人たちは、毎日かくじつに、わたしたちに新しいせかいをはこんできてくれているのだ。明日も早おきして、かんしゃの気もちをこめて言うよ。
「おはよう、お兄さん」
「おはよう、わたしがまだしらない、新しいせかい」

「暗闇の中、新聞を積んでさぁ出発です」
(京都新聞社)
キラキラの笑顔

「毎朝笑顔で新聞を届けます」
(北國新聞社)
私の住む地いきには、30年い上も新聞配達をつづけているおばちゃんがいます。おばちゃんは、なんと今年80さいです。雨の日も、冬の寒い日も、朝早くから毎日休まず、新聞を配っていると聞いて、びっくりしました。体は小さいけれど、とってもパワフルで、笑顔がかわいいおばちゃんは、いつも会うと、私にやさしく声をかけてくれます。
この前、「毎朝、新聞配達をしているから、けんこうにしてもらって、本当にありがたいのよ」と話しているのを聞いて、すごいな、と思いました。一つのことを毎日かかさず、30年もつづけることは、かんたんなことではないと思います。いつも感しゃの気持ちで、新聞配達しているおばちゃんは、キラキラかがやいていて、私も勇気がわいてきます。新聞配達は、たくさんの人を元気にする、すてきなお仕事だな、と思いました。私もおばちゃんのように、いつも感しゃの気持ちをわすれないで、いろいろなことにちょうせんしていきたいです。

「毎朝笑顔で新聞を届けます」
(北國新聞社)
幸せの花束

「新聞到着『急げ~』」
(読売新聞社)
「えっ。こんなに気を付けることがあるの?」
僕が初めて、母の新聞配達を手伝った時はおどろきの連続だった。「風で新聞が開かないように」「雨でぬれないように」「種類や数をまちがえないように」配達中は一しゅんたりとも気が抜けない。でもこんな思いで配ってくれている人がいるから、今僕は新聞を読めるのか。どんどん感謝がこみあげてくる。
そんな配達のと中には、素晴らしい景色に出合うこともあった。朝焼けのみかん色の空。まん丸のお月さま。思わずはっとする。これは新聞配達のごほうびだ。
もう一つごほうびがある。それは地域の方が「ありがとう」と声をかけてくれることだ。他のどんなごほうびよりもうれしかった。
配る人も読む人もうれしい気持ちになれる新聞。自転車カゴに入ったたくさんの新聞は、幸せのバラの花束だね、お母さん。

「新聞到着『急げ~』」
(読売新聞社)
(敬称略)