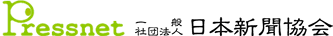- トップページ
- 刊行物
- 新聞協会報・スポットライト
- 患者に寄り添い生の尊さ訴え
2009年 2月17日
患者に寄り添い生の尊さ訴え
京都「命ときめく日に」
力のこもった、医療現場の報告である。昨年十一月に第一部「癌(がん)から始まった」(八回)を、元旦から第二部「先端医療届く時」(七回)を掲載した。
第一部はさまざまながん患者の生き方を描いた。第一回は二歳のとき脳腫瘍(しゅよう)が見つかった男の子の闘病で、母親の看病や、同じ病棟のお兄ちゃんとの心温まる交流が描かれる。小児まひと自閉症の息子を育て上げたら自分が大腸がんになってしまった女性も登場する。歌手・高石ともやさんの妻は大腸がんで余命半年と宣告されたが、家族に支えられ既に二年たつ。
第二部は最先端医療の報告である。ラクビーの練習で首の骨を折り、首から下がまひした青年はiPS細胞の再生医療で失った機能を回復させたいと期待する。一方、京都大学のiPS研究者は「過度な期待を与えると患者さんにとってもひどいことになる」と自戒する。筋肉が徐々に萎縮(いしゅく)する「遠位型ミオパチー」という難病は患者が全国に三百人。治療法はほぼ分かったが、薬にすることは難しいという。市場規模が小さいのでメーカーが尻込みするようだ。国は研究には補助金を出すのに、薬にすることはできないなんておかしい、と研究者は怒る。三百人といえども、わらにもすがりたい気持ちは同じはず。資本の論理で切り捨てていいのかという問いは重い。患者だけでなく、研究者も取材して両方の思いを描く手法が、内容に厚みを出している。
記者は患者の人間関係に寄り添って、まるで応援歌を歌うように記事を書いている。患者の姿勢も前向きで、写真はみんな笑顔だ。
「生きる尊さを思い知らされました」と反響も多数寄せられた。社会報道部取材班の高田敏司編集委員は「自殺も多いし、将来への漠然とした不安も根強いこの時代に、命の大切さを訴え続けたいと思う」と語っている。(審査室)