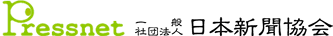- トップページ
- 刊行物
- 新聞協会報・スポットライト
- 模擬裁判での心の動き追う
2009年 6月2日
模擬裁判での心の動き追う
岐阜「変わるぎふの法廷 裁判員になる市民」
4月に始まった連載は第1部(地裁)、第2部(地検)、そして6月掲載予定の第3部(弁護士)まで、法曹三者が裁判員裁判に向けて模索する姿を追い、制度の課題を探る。その中で「模擬裁判」に参加した市民が審理や評議にどうかかわり、何を感じたか、克明に描き出しているのが目に付く。
岐阜地裁で最も大きな3階の法廷。裁判員役の54歳の女性は法廷の雰囲気に驚いた。難解な法律用語が飛び交い、異様な圧迫感すら覚えた1年前の見学時とはまるで違う。岐阜地検の検事はアナウンサーのようにゆっくり、丁寧に事件の概要を説明。「未必の殺意」は「死ぬかもしれない、死んでも構わない」に言い換わった。弁護人も映画俳優のように身ぶり手ぶりを交えて弁論する。
それでも、初の体験に戸惑いは隠せない。心神喪失で無罪にはしたが、「人を殺したのに裁けないなんて」と、裁判員たちは一様に釈然としない表情を浮かべた。評議の冒頭に裁判官から説明を受けても、有罪・無罪の判断基準で「合理的な疑いって何?」と首をかしげ、殺意の有無で「殺すつもりはなかったと言ってるよ」と被告人の言葉に気持ちが揺らぐ人も多い。有罪認定後にもめた例も。有罪に納得できない裁判員が「冤罪(えんざい)の可能性がないとも限らないから」と執行猶予を求め、裁判官から「量刑は有罪を前提としてもらわないと」とたしなめられた。
一方で、模擬裁判で、「自分も裁判に参加している」と実感した人、判決にかかわった達成感を覚えた人もいたことを連載は伝える。桐山圭司報道部長は「自分が実際に裁判員に選ばれたとき、もう一度連載を読んでほしい」と語る。第2部まで同部の河合修記者が担当。各回に証拠の評価、責任能力などについてミニ解説が付き、読者の理解を助ける。(審査室)