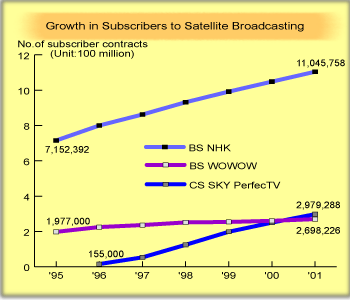|
NSK ニュースブレチン オンライン ------------------------------------------------------------------- 憲法が保障する「表現の自由」を脅かすとして、ジャーナリストやメディア関係者、学者らが反対している人権擁護法案が4月24日、個人情報保護法案が25日、国会で審議入りしたことから、新聞協会理事会は、24日、緊急声明を発表した。 新聞協会理事会が声明をだすのは、1987年5月の朝日新聞阪神支局襲撃事件以来15年ぶり。新聞協会が両方案の国会提出にいたるまで、繰り返し「報道の自由」に十分配慮するよう求めてきたにもかかわらず、法案は「表現の自由に政府が介入する道をひらくもの」となっていることを批判、報道による人権やプライバシー侵害の問題は、報道機関の自主的な対応で解決を図るべきとした。 新聞協会の緊急声明と前後して、放送・出版業界や地域の報道機関も声をあげた。 民間放送連盟の氏家斉一郎会長は25日、2法案について「表現の自由を侵す内容で、断固反対」との談話を発表した。作家やジャーナリストらでつくる「個人情報保護法案拒否!共同アピールの会」も「この法案は、報道・表現の自由を殺そうとしている」との生命を発表した。作家の城山三郎氏(74歳)は、「軍国主義を進め、言論・表現の自由を奪った治安維持法の再現だ」と批判した。日本書籍出版協会、日本雑誌協会も同日、2法案に反対する共同談話を発表した。 それぞれの地域の新聞・通信・放送各社の報道責任者らも「報道の自由、表現の自由の侵害につながる」などと批判する共同声明を相次いで発表、それぞれメディア規制は容認できないとした共同見解、共同声明を発表、地元国会議員や自民党、公明党などに提出した。 報道責任者らが声をあげた地域は、福井県、青森県、岩手県、山梨県、札幌市、名古屋市、福岡市。このほか、放送局の番組審議会や、テレビ朝日をキー局とするANN系列の中部ブロック5社の社長会も3法案に反対している。今後さらに増える見込み。 国会では、野党議員らの質問に対して、人権擁護法案については、森山真弓法相が「報道界の自主規制の状況を見れば、犯罪被害者などへの取材に関し、一定の制度の中での実効的救済措置が必要だ」と答弁、個人情報保護法案については、小泉純一郎首相が「報道・表現の自由を侵害するものではまったくない。メディアを規制する意図はない」などと答弁した。 今国会は6月19日まで。国会審議の状況を見極めながら、新聞協会はじめメディア関係団体は法案反対の活動を展開することにしている。 新聞協会編集員会は、4月18日に開かれた4月度委員会で集団的過熱取材対策小委員会を設置することを決めた。 編集委員会は、昨年12月度委員会で「集団的過熱取材(メディアスクラム)について取材者が守るべきガイドラインをまとめた「見解」を発表したが(1月号既報)、小委員会は、この「見解」を前提に、現場レベルで調整・解決できない過熱取材をめぐる問題を協議する裁定権限を持った編集委員会の下部組織として新聞・通信、NHKの15社で構成し、5月8日に発足する。 当該地域の記者クラブや支局長会から現場解決が困難との申し立てがあった場合、小委員会幹事の判断により、小委員会が引き取り、直ちに解決を図る。過熱取材の被害者から小委員会に直接申し立てがあった場合は、速やかに当該の支局長会に連絡、調整にあたらせる。裁定の内容はそのつど小委員会で協議し決定する。裁定結果は速やかに現場に連絡、必要に応じて公表する。 公人や公共性の高い人物からの申し立ては基本的には受け付けない
今回のテーマは「日本のメディア・マネジメント」。朝日、読売、信濃毎日、西日本、中日の各新聞社の幹部らと新聞経営について懇談したほか、NHKの理事、報道局長と懇談、ニュースセンター、ハイビジョンテレビなどを見学、ローカル局の西日本テレビの幹部とも懇談した。東京最後の日は「ユニクロ」ブランドを中国で作っているファーストリテイリング東京本部を訪問、東京・渋谷の「ユニクロ」店舗を視察した(写真)。このほか、広告会社の電通や外務省、トヨタ、松下電器産業、関西経済連合会なども訪れた。 参加者は以下のとおり。
|
 日本新聞協会と全国中華新聞工作者協会による日中記者交流計画は、日中国交30周年にあたる今年、20回目を迎えた。4月7日来日した中国側記者団11人は、東京のほか、新潟県、長野県、愛知県、京都府、福岡県を訪れる2週間の日程をこなし、21日福岡から帰国した。
日本新聞協会と全国中華新聞工作者協会による日中記者交流計画は、日中国交30周年にあたる今年、20回目を迎えた。4月7日来日した中国側記者団11人は、東京のほか、新潟県、長野県、愛知県、京都府、福岡県を訪れる2週間の日程をこなし、21日福岡から帰国した。 同研究所が昨年発表した「技研中長期ビジョン」によれば、(1)放送用デジタル伝送路と通信系のネットワークを活用したサービスの研究(2)コンピューター、ネットワーク、サーバーなどを使ったコンテンツ制作技術に関する研究(3)ハイビジョンを超えるテレビシステムを立体テレビの研究、撮像、記録、表示技術に関する研究――の3点を、今後の技研の研究の柱としている。新技研は、これらの研究活動に対応するため建設された。 1階のエントランスには400人収容可能な講堂や技術展示コーナー、情報コーナーなどを設置。視聴者や地域住民に開放している。
同研究所が昨年発表した「技研中長期ビジョン」によれば、(1)放送用デジタル伝送路と通信系のネットワークを活用したサービスの研究(2)コンピューター、ネットワーク、サーバーなどを使ったコンテンツ制作技術に関する研究(3)ハイビジョンを超えるテレビシステムを立体テレビの研究、撮像、記録、表示技術に関する研究――の3点を、今後の技研の研究の柱としている。新技研は、これらの研究活動に対応するため建設された。 1階のエントランスには400人収容可能な講堂や技術展示コーナー、情報コーナーなどを設置。視聴者や地域住民に開放している。