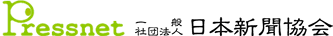- トップページ
- 新聞協会報・地域を伝える(旧・記者駆ける)
- がん終末期描き「家族」問う
2015年 2月24日
がん終末期描き「家族」問う
中日「未完の論文―ある社会学者の死」
虐待や依存症などを研究しながら、自らの家族問題で痛恨の思いを抱いた社会学者。その壮絶ながん終末期を5回連載(2月10日~14日付)で描き、読者に人生、仕事、家族の意味を問うた。
主人公は、2014年6月に死去した名古屋市立大学・石川洋明教授。重い前立腺がんを患うなか、妻が12年9月、無理心中を図って小学生の長男を殺害した。妻は病が進む石川の姿を見て、うつ病を悪化させていた。
石川は事件を論文にまとめようと志す。だが、妻は執行猶予付き判決を受けたあと、14年5月に精神科病院で自殺。なおも論文への執念を燃やすなか、自らの命も尽きる―。
連載を担当した安藤明夫編集委員は、子どもの虐待を防ぐ市民団体で20年前に石川と知り合った。数年後に石川が団体を離れ疎遠になっていたが、同じ大学で非常勤の講義を持ったことから、妻の自殺の翌週に再会。石川は、顎の骨が壊死(えし)し車いすに乗りながらも教鞭(きょうべん)をとっていた。
食事を約束したが、仕事の事情で延期した。石川の死は、その10日後。終末期だと知ってはいたが、思いもよらぬ早さだった。激しく後悔した安藤氏は、大学関係者の悲しみと石川の論文への志を知り、記事で伝えようと決意する。
無理心中について心の奥深くに入って話を聞く難しさは、過去の取材経験から熟知していた。学術研究も少ない。当事者となった石川が何を伝えたかったのか。そして、終末期の激しい生き方に秘められたものは―。同僚や医師、学生など20人以上に取材した。
「全面的に礼賛するような記事にはしなかった。もっと積極的にヘルパーなどの支援を受けるべきだったのに、自負心が強く問題を抱え込んでしまった。それも含めて描いた」と安藤氏は語る。本質を考えるうちに、草稿が跡形もなくなるほど書き直したという。(洋)