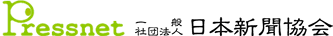- トップページ
- 新聞協会報・地域を伝える(旧・記者駆ける)
- 社会に戻る道を伝える
2015年 9月22日
社会に戻る道を伝える
山梨日日「扉の向こうへ―山梨発ひきこもりを考える」
介護士の訪問で初めて、ひきこもりの家族がいると分かることがあるらしい―。取材開始当初、山梨県内には彼らを支援する組織が皆無だった。「ひきこもりが見えない存在になってしまっている例は多いのではないか」(前島文彦企画報道グループキャップ)との思いが、6人の取材班の出発点だ。昨年8月から今年6月まで9部構成で計65回展開。連載終了後も続報を掲載している。
前島氏は「世間体を気にして隠しているケースも多く、当事者や家族を探すのはとても難しかった」と振り返る。NPО法人「全国引きこもりKHJ親の会」に相談したところ、山梨県支部の立ち上げを目指してシンポジウム開催が決まった。その参加者を端緒に取材を始めた。
長期化し、当事者や家族が高齢化しているケースも少なくない。20年間ひきこもっている息子を持つ老夫婦は「自分たちが死んでしまったらどうなるのか」と深い悩みを打ち明けた。当事者には「分かりやすい質問」ではなく「話しやすい質問」を心掛け、答えを遮らないよう注意した。疑問点や確認事項は次の機会に聞き、何度も取材を重ね信頼関係を築いた。
甘えて怠けている連中のことをなぜ取り上げるのか、といった反応もあった。しかし、前島氏は「生きにくい格差社会の中では、誰もがひきこりになる可能性がある。ひきこもりになっても社会に戻る道はあると伝えたかった」という。
「記事で周囲の理解が進み、悩みを打ち明けられるようになった」と話す親や、取材がきっかけで外に出られるようになった当事者もいる。来月には県に専門の相談窓口が設置されるなど、この1年で県内の状況は大きく変わった。前島氏は「地域社会の理解を深めるためにも、地元紙が恒常的に情報発信していかなければならない」との思いを新たにした。(愛)