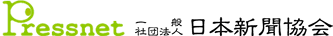- トップページ
- 新聞協会報・地域を伝える(旧・記者駆ける)
- 遺骨収集の現場 執念で報道
2020年 1月14日
遺骨収集の現場 執念で報道
北海道「残された戦後 記者が見た硫黄島」
東京支社報道センターの酒井聡平記者は、戦時中に小笠原諸島・母島の警備隊兵士だった祖父の軍隊手帳を見たのを機に、硫黄島に関心を持った。苫小牧民報の記者だった2006年、政府の遺骨収集事業に参加する当時70代の男性を取材。以来、現地に行きたい思いを募らせていた。
硫黄島は戦後、米軍や自衛隊の拠点となり関係者しか上陸できない。遺骨収集派遣団への現地取材も認められていない。北海道新聞社に転職した酒井記者は、それでも関係者への取材時に硫黄島への思いを訴え続けた。昨夏、関係団体の幹部から「派遣団に推薦できる」との話が舞い込んだ。記者としてでなく「母島の兵士の孫」として。
島に渡れる千載一遇の機会を得たが、派遣団の一員として赴くため記事化できない可能性もあった。上司はそれでも「星の位置まで記録すべきだ」と送り出してくれた。
滞在期間は19年9~10月の2週間。総勢37人が遺骨の収集作業に当たった。団員は1日5時間、壕(ごう)内の土砂をスコップで掘り、遺骨を探した。壕内は地熱で蒸し風呂状態。爆雷やサソリ、崩落事故の不安にさいなまれた。
作業中の取材は禁止。酒井記者は休憩中に参加者から話を聞き、宿舎に戻ってから記録した。ある50代の男性は「遺骨収集のことはほとんど知られていない。多くの人に伝えてほしい」と語ったという。
硫黄島での遺骨収集の様子を伝える報道は前例が少ない。12月11日付に初回が載るまでは不安だったと振り返る。全4回で収集事業の現状や参加者の声を紹介した。
硫黄島戦没者1万1千人の遺骨は今も収容されていない。元島民の帰還も許されないままだ。戦争の悲劇は子、孫世代にまで尾を引いている。「現政権は『戦後』を終わらせたがっていると感じる。風化にあらがいたい」と酒井記者。(斎)