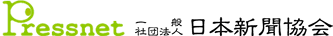- トップページ
- 新聞協会報・地域を伝える(旧・記者駆ける)
- 官民双方の災害対策追う
2020年 6月23日
官民双方の災害対策追う
長崎「備えはいま 普賢岳大火砕流から29年」
火山灰の下から収容した消防車やパトカーの展示を前に、長崎県島原市消防団第15分団の古川進一郎さんが口にした。「災害の記憶が薄れるとともに、展示車両が少しずつ朽ちているのが分かる」。5月下旬、北上木場農業研修所跡の清掃活動で島原支局の大田裕記者に語った。
報道関係者を含む43人が犠牲になった雲仙・普賢岳大火砕流から6月3日で29年がたった。溶岩ドーム(平成新山)は地震や豪雨による大規模崩壊の恐れがある。有事の避難に備えた地域防災組織や自治体などの対策を5月31日付から3回に分け報じた。
大田記者は消防や警察経験者らを代表に据えた地域防災組織「自主防災会」の活動に着目。島原市の安中地区は若年層向けの避難訓練や防災マップ作りなどに取り組む。「命を守るために住民自らが率先して災害に備える」と横田哲夫会長。川を挟んで隣接する南島原市深江町との初の合同訓練も計画している。
避難所の備えにも迫った。噴火災害当時の避難者からは「床が硬くて寝られなかった。プライバシーもない」との声が聞かれた。島原市は段ボール製の間仕切りとベッドを準備し、避難生活の負担軽減を図る。
間仕切りは新型コロナウイルス対策としての効果も期待できる。飛沫拡散を防げるからだ。しかし国の通知に基づき世帯ごとの間隔を取れば、当時7208人に上った避難者を収容し切れない。市の担当者の苦悩も取り上げた。
29年前、報道陣が殺到した研修所跡近くの「定点」には、今も取材車両が野ざらしのまま残る。マスコミが消防団員らを巻き添えにした、との批判は依然消えないと大田記者。「次の災害に備える仕組み作りを紙面で伝え、支援したい」。市民の厳しい目と向き合いながら、30年の節目へ取材を続ける。(海)