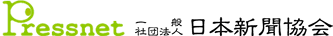- トップページ
- 新聞協会報・地域を伝える(旧・記者駆ける)
- 里子巡る自身の体験つづる
2023年 2月14日
里子巡る自身の体験つづる
中日・北陸中日「家族になろうね~特別養子縁組で子どもを迎えて」1月5日~(継続中)
「お願いしたいお子さんがいる」。社会部の奥田哲平記者(現北陸本社報道部)は2020年8月、名古屋市の児童相談所から里子の受け入れを打診された。生みの親が育てることができなくなった子を迎える里親を、戸籍上も実親として扱う制度「特別養子縁組」が前提だった。里親登録から4年。心ははじめから決まっていた。翌日、夫婦で児相の担当者に子を受け入れる意向を伝えた。
不妊治療を経て特別養子縁組で子を迎え、40代で父親になった奥田記者。自身の体験と、そこから見えてきた特別養子縁組を含む里親制度の現状、課題をつづった。
子の生みの母は妊娠が判明してから「一人では育てられないけれど中絶はしたくない」と思い悩み、里子に出すことを決めたという。生みの母は葛藤し続ける。子を手放した後も児相の担当者に電話で複数回、「本当にこれで良かったのか」と尋ねていた。奥田記者はそれを児相の担当者から明かされたときのことを連載で振り返った。
制度上、子を迎えてから半年間の試験養育期間を経て縁組が成立するまでの間に生みの親が心変わりすれば、預かった子を返す可能性がある。奥田記者は連載で「想像するだけで胸が締め付けられた」と明かした。里親制度は「生みの親も、子を受け入れる親も葛藤の連続だ」という。それでも「いろんな家族の形があっていいし、なきゃいけない」。
奥田記者は里親制度が広く知られることを望む一方で「生みの親が養育に困難な状況にあるなら里子に出せばいい、と周囲が安易に考えることには賛同できない」と強調する。「難しい状況下で子を育てる親も肯定されるべきだとの思いもある」という。
自身の家族については「多くの『典型的な家族』とは少し違っているかもしれない」とした上で「でも、私たちは確かに存在し、毎日を楽しく生きている」と報じた。連載を通じて「多様な家族の在り方が当たり前に受け入れられる社会の実現に貢献したい」と話す。(浅)
※連載はこちらでご覧いただけます。(他社サイトに移動します)