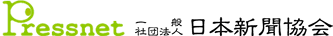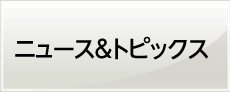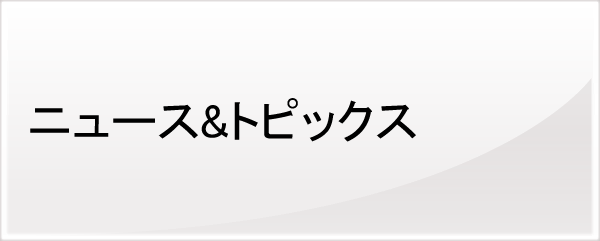- トップページ
- 新聞協会報・紙面モニターから
- 平和国家 原点見つめ直す時 地方紙各紙の元日付紙面
2025年 1月28日
平和国家 原点見つめ直す時 地方紙各紙の元日付紙面
SNS 選挙への影響に警鐘
2025年は昭和100年にあたり、普通選挙法制定から100年、戦後80年、阪神・淡路大震災30年などさまざまな節目を迎える年である。元日には、能登半島地震発生から1年を迎えた。地方紙の元日付社説・論説には、節目に際し、民主主義や平和、防災などをあらためて問い直すものが多くみられた。今年は参院選が行われることもあり、昨年の衆院選や首長選の結果にも大きな影響を与えた交流サイト(SNS)の功罪に注目したものも複数あった。
戦争体験の継承課題
岐阜は、戦後80年について「日本が育んできた戦後の価値観は、戦前から続くナショナリズムの心情と、民主化や自由への希求との間で形づくられてきた。二つの思想の相克はいまも底流で続いているが、結果として日本は80年にわたって非戦を続け、経済大国として国際的に貢献してきた。この歩みに誇りを持つことは、的外れとは言えまい」と総括した。
静岡は「荒廃した国土から戦後が始まった日本は、この80年間を平和国家として歩んできた。厳しい国際情勢の中でもその歩みを続けるには、世界の安定に力を尽くさなければならない」と主張した。さらに、「西側諸国の一員でアジアの主要国でもある日本でなければ果たせない役割があるはずだ。国民一人一人がその役割を考えることが重要だ」と指摘した。
河北は「存する東アジアにおいて、地域諸国の警戒心を刺激することなく緊張を解きほぐす、友好の芽を育てる、そんな国でありたい」と提案した。茨城も「失敗の歴史の反省を踏まえれば、防衛力の増強に頼るのではなく、対話を軸にした外交で各国との友好関係を築き、不毛な戦争に至らぬよう努めることが肝要だ」と強調した。
一方、北海道は「日本政府は従属的な対米関係の下で自衛隊の増強と米軍との一体化を加速させている。集団的自衛権の行使を認め、敵基地攻撃能力の保有を決めた。憲法の平和主義が揺らいでいる」とした。その上で、「『戦争ができる国』に逆戻りする流れを止めねばならない。自由で公正な社会を守るため、平和と民主主義を誓った戦後の原点を見つめ直す時である」と訴えた。
上毛は「終戦から80年。遠い過去となりつつある先の大戦の記憶をいかに継承していくかが問われる時代となった」と指摘した。西日本も「一人一人が戦争のイメージを『経験』として積んでいく。戦争を二度と起こさないためにできることであろう」と、「伝える」重要性を強調した。
米軍による広島市と長崎市への原子爆弾投下も80年を迎える。中国は、24年のノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(被団協)が「証言の大運動」を展開していくことに触れ、「被爆者がいなくなる日が近づいている。いつまでも頼れるはずがない。次の世代に証言を伝え継ぎ、国内外に広げていく。縦に横に、核廃絶へのうねりを生み出していく。その決意を私たちが示す番である」と主張した。
長崎も「戦争、原爆を体験した人は高齢化し、その数は減り、記憶を語る場、学ぶ場は確実に減っている。5歳時の記憶を持つ人は85歳になり、体験を直接的に聞く機会はもうじきなくなるのが現実だ」とし、「記憶を引き継ぎ、語り継ぎ、広めることの意味がいっそう問われる節目になる」と指摘した。
沖縄戦終結からも80年となる。沖タイは「沖縄では、戦争が過ぎ去った過去の出来事として完了することがない。生活の場が砲弾の飛び交う戦場となり、戦後は基地と隣り合わせの生活。米軍による事件事故や爆音に接するたびに、沖縄戦の記憶がよみがえる」とした。その上で、「基地によって日常生活が脅かされるようなことがない当たり前の暮らしは、いつになったら実現するのだろうか」と嘆いた。琉球は「沖縄の島々が地上戦と猛爆にさらされ、多くの県民が犠牲となった年から今日までの歩みを振り返り、望ましい沖縄の姿を見定める年としたい。沖縄戦と戦後体験は、未来に向かって県民が歩む時の道標となる」との見方を示した。
今年は昭和100年にあたる。佐賀は昭和時代について「64年に及んだ『昭和』を振り返るとき、どの時代を過ごしたかで見方は大きく異なる。前半には弾圧と死と破壊と飢餓があった。やがて復興と成長を果たし、欲望と狂乱の祭りのような終盤を迎えることになる」とした。その上で、「そのように概観すると、昭和がノスタルジーで語られるほど『いい時代』であったかどうか、議論の余地があるだろう」と、一部に出ている「昭和礼賛」に疑問を呈した。
災害巡り共助の尊さ強調
発生から30年となる阪神・淡路大震災は、日本にとって地震対策を見直すきっかけともなった。1年を迎えた能登半島地震の被災地は、依然として復興途上にある。福井は阪神・淡路大震災の節目に際し、「1995年の阪神大震災から17日で発生30年を迎える。災害関連死が認められるようになったのはこの震災からで従来の地震対策を一変させたといわれる。30年が経過しても対策はなお有効なのか。議論を深める年にしたい」と提案した。北日本は能登半島地震の被災地の現状について、「避難所の環境が100年前から変わらないというのは情けないことだ。我慢して過ごさねばならない場所とせず、被災から立ち上がる元気をもらえる場所とする必要がある」と訴えた。
北國は「今年は阪神大震災から30年となる。この震災を機にNPOが育ち、東北、熊本など各地の被災地支援を経て、ボランティアは公的役割を担う重要な存在になった。住民とのつながりを深めた多くの支援者、多様な縁の広がりは、被災地の大きな財産である」と、この30年に起きた災害を通じて育まれた共助の精神の尊さを強調した。
神戸は、中央防災会議のワーキンググループが昨年11月に出した報告書で、自治体がNPOなどとの連携体制を全国規模で作る必要性に触れた点について、「行政が担うべき公助までも、NPOなどに肩代わりさせる意図が読み取れる。団体の規模や専門性でボランティアを分断し、上下関係を持ち込む発想は、管理を容易にし、個人の自由な活動を阻む恐れがある。統制を強めようとする動きには、敏感でいなければならない」と主張した。
今夏の参院選について、徳島は「『何も変わらない』と諦めるのはやめ、SNSに惑わされずに、未来への思いを投票で示すべきだ」と呼び掛けた。新潟は「SNSは強い情報の拡散力を持つ半面、負の感情を瞬く間に広める怖さがある」と指摘した。信濃毎日も「SNSで世論を操れば選挙の勝利に直結する現実。ノウハウは既に確立されつつある」と注意を促した。
東奥は「今年は、男性のみとはいえ納税要件が撤廃された普通選挙法制定から100年となる。民主主義の基盤である自由で公正な選挙が揺らぐ兆しが見られる今、民主主義の大切さを再認識し、分断の危機に立ち向かいたい」と強調した。
ニュース19紙、企画・連載57紙
【1面トップ】19紙がニュース、36紙が企画、21紙が連載でスタートした。ニュースと連載の主な見出しを拾う。
《ニュース》河北「『多賀城政庁』復元へ 宮城県、観光振興を強化」、静岡「迎撃『配備要図』か 駿河区沿岸の作戦記す 終戦直前 米軍静岡上陸に備え 元守備部隊員宅で発見」、中日「能登教訓に代替水源強化 民間所有の井戸活用 愛知県、新年度予算へ」、中国「核否定 原点の体験記 『さいやく記』原本見つかる 故森滝市郎さん 生々しい被爆の記憶1日ごとに刻む」、琉球「県出身者1歳と18歳最多 平和の礎刻銘14.2万人分データ分析」
《1面連載》東奥「新たな挑戦へ 青森リンゴ植栽150年」、山形「県人口100万人割れ その先の山形新章」、下野「平和のかたち とちぎ戦後80年」、上毛「昭和100年 故(ふる)きを温(たず)ねて」、宮崎日日「日向灘 脅威と向き合う」、沖タイ「悲(なちか)しや沖縄(うちなー) 戦争と心の傷」(審査室)