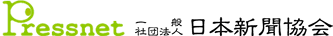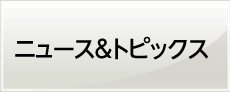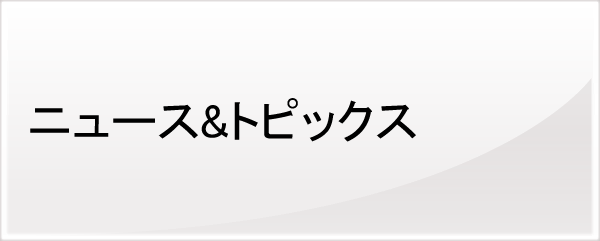- トップページ
- 新聞協会報・紙面モニターから
- 政策転換への懸念相次ぐ トランプ米大統領が就任
2025年 2月11日
政策転換への懸念相次ぐ トランプ米大統領が就任
気候変動対策後退に批判多数
1月20日に就任した米国のトランプ大統領は2017~21年の第1次政権、昨年の選挙戦とその勝利後から物議を醸す政策・発言を多く打ち出している。各紙の社説では懸念や注文、苦言が目立った。同氏は、カナダが米国の「51番目の州」になるべきだとし、デンマークには自治領グリーンランドの売却を求めた。両国はともに、米国と同じく北大西洋条約機構(NATO)加盟国。東奥は「目に余る好き放題の主張」と批判した。
グリーンランドは北極方面の脅威から米国を守る位置にあり、既に米軍基地を受け入れている。下野、長崎、大分合同などは、同氏の発言が「同盟国の信頼を踏みにじる」とし、中ソの脅威に備えるなら基地の機能拡充など「正々堂々と外交を展開」すべきだと提言した。
イエスマンで固めた政権
20日の就任式は40年ぶりに屋内、連邦議会議事堂内で開催された。議事堂は21年1月、その前年の大統領選で同氏が落選したことに不満を募らせた支持者が襲撃事件を起こした場所。神戸は「歴史の皮肉と言うべきか」と記した。
式典には忠誠を誓う閣僚、トランプ氏に接近したIT企業経営者らが出席。読売は「イエスマンで固められた内向きな2期目政権を象徴するかのようである」と評した。20年大統領選で敗れ、複数の案件で訴訟や捜査の対象となった同氏の「報復」したいとの執念や、イーロン・マスク氏ら大富豪重用の行き過ぎも懸念。返り咲きを支えたのは「物価高に悩む庶民」であることを思い起こすとともに、連邦議会上下両院で与党共和党が過半数であるとの「有利な状況を生かした民主的な政策遂行を心がけてほしい」と呼び掛けた。
連邦最高裁判所も、第1次政権が送り込んだ保守派判事が多い。西日本は「三権分立のバランスが崩壊する危機」にあると書いた。
中日・東京は「1776年の独立宣言が掲げた自由と平等の精神は、多様な生き方を認める寛容さの基盤となり、世界中から多彩な才能が集う米国の魅力にもなってきた」とし、マスク氏も南アフリカ出身だと指摘。山形や佐賀なども、建国の父たちが「多数派の専制」を恐れた歴史を振り返った。
議会襲撃事件に関与した極右を含むトランプ氏支持派、同批判派はそれぞれ街頭でデモを実施。毎日はそこに「米国の分裂」を見て取った。事件の服役囚に恩赦を与えるとの表明を巡っては、高知が「政治的暴力を許容する風潮につながる」と危惧する。
トランプ氏は就任演説で「米国の黄金時代が今始まる」などと語り、「米国第一(主義)」を強調。「格調の高さを感じさせる内容ではなかったが、従来の主張に沿った分かりやすい演説」(静岡)だった一方、「これが『偉大な国』なのか」(毎日)との指摘もあった。不法移民の流入防止や送還、輸入品への高関税、地球温暖化防止のためのパリ協定からの再離脱と化石燃料増産などの政策は、大統領令で次々と実行に移されている。いずれも「前政権の政策の大転換」(新潟)だ。ただ、従来の主張でもあり、岐阜などは「予想通りの衝撃」を内外に与えたと記した。
関税引き上げは国内産業保護、特に製造業での雇用拡大効果を狙う。徳島は「物価は上がり、インフレが進めば、困るのは米国民」と指摘。対抗措置や条件交渉の段階へ移った中、「性急に導入すれば各国が報復関税に動く可能性が高く、世界中で経済成長の障壁となる危険をはらむ」(愛媛)懸念がある。
バイデン前政権の気候変動対策を覆す大統領令には批判的な論調が多い。茨城は「強い非難に値する」とし、企業や米国以外の国が追随すれば「国際的非難の対象」になるとした。一方、産経や北國は、エネルギー安保などの観点から、一定の理解を示した。
就任演説で打ち上げた火星有人飛行計画に対しては「世界に夢を与える挑戦」(上毛、山梨日日など)との見方もある。
日経は、イスラエルとハマスの停戦合意について、同氏が「就任前から働きかけ」「一役買った」ことを挙げる。ウクライナでの和平仲介にも同氏は意欲を示すが、「ロシアに譲歩した形で幕引きを図るなら、力ずくで現状を変える試みを許すことになる」(信濃毎日)など憂慮も聞かれる。
日本外交の主体性問う
米国の民意に「米国復活への渇望」(南日本)は根強い。朝日は、同氏流の外交について「もはや特異な過渡的現象とは言いがたい」とし、国際社会のあり方や日本の針路を「主体的な思考」で描くことを提唱した。岩手日報も「日本外交の主体性」が問われると強調。石破首相が早期に訪米し、高関税政策のデメリットや国際強調の重要性を説けるよう関係を深めるべきだと主張した。同時に「予見不可能な言動に振り回され続けないため」に、食料自給率向上や内需拡大に取り組むことも訴えた。(審査室)