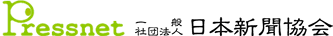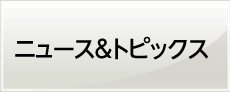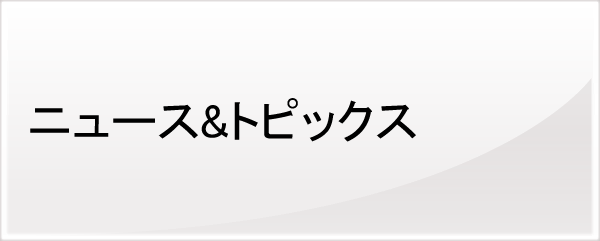- トップページ
- 新聞協会報・紙面モニターから
- 地域コミュニティー再生を 東日本大震災14年
2025年 4月8日
地域コミュニティー再生を 東日本大震災14年
南海トラフに備え訴える
東日本大震災と東京電力福島第1原発事故から今年で14年となった。再生・復興の取り組みが続く中、今なお避難生活を余儀なくされている住民も多い。地域コミュニティー再生の道のりは困難で、新たな課題も生まれている。その後も大きな災害は続いており、将来の南海トラフ巨大地震への対応も必要だ。政府は原発について最大限活用する政策への回帰を打ち出している。各紙の社説・論説は、産経が「次の試練に備えなくてはならない。地震は防げないが、被害は減らせることも学んだ」と強調したように、今こそ大震災の教訓を、社会に生かすよう求めた。
自助、共助の大切さ指摘
岩手日報は復興を巡り「地域の未来を開くには心のケアに加え、なりわい再生や子どもの教育支援などが欠かせない」と主張した。福島民報は「帰還した住民も含めたコミュニティーを形成し、より良い地域を共に目指す絆を強める取り組みも重要になる」と指摘。被災地で直面しているのは日本社会が抱える課題だとして熊本日日は、被災しても「必ず生活を取り戻すことができるという実例を東北の地で示したい」と期待した。
国の財政支援で建設された施設が活用されず、負担となる場合もある。日経は「復興庁は復興事業が被災地にもたらした新たな課題もしっかり検証すべき」だと強調。読売は「将来像を描き、地に足のついた現実的な街づくりを進める」視点も重要だとした。被災地で実施された宅地の高台移転や、かさ上げされた土地が十分に利用されていないとして南日本は「空き地の活用とコミュニティー再建への工夫が急務だ」と述べた。北海道は「国は支援のあり方や実効性を不断に検証し、古里再生の道筋を確かなものにすべきだ」とした。
医療の重要性を指摘したのは中日・東京だ。「救えたはずの命を真に救えるよう、今後、規制緩和も検討する必要がある」とドローンの自由な飛行やオンライン診療などの活用を訴えた。
政府は来年度中に災害対応の新組織として防災庁を設置する方針だ。毎日は防災庁について「被災者のニーズを把握し、事前に関係組織との調整を進めることが求められる」と注意喚起した。
大きな地震を経験した新聞各紙も災害対応の検証を訴えた。新潟は課題の検証を通じ「被災の実態や悲しみを忘れないこと」が防災につながると指摘。北日本は「行政側が大きな被害を受け、混乱し、長期にわたり支援の手が届かない事態」を想定する必要性に言及。福井も「自治体が十分に機能しない事態に直面し、自助や共助の大切さが再確認された」と戒めた。
北國は、災害公営住宅の過剰な建設は自治体の負担になるとし「身の丈に合わぬ過大な投資」が大震災の重要な教訓の一つだと結論付けた。神戸は「未来に何を残すのか。より小さなまとまりを大事に、住民らが主体的に考えられてこそ、時代や環境の変化にも対応できるはずだ」と述べた。
多様な主体の事前復興重要
南海トラフ巨大地震対応も急がれる。静岡は「避難場所や避難ルートを確認して、すぐに動ける態勢を取ることが欠かせない」とし、神奈川は「多様な被災パターンを想定し、事前に対応策を話し合っておく必要がある。幅広い主体による『事前復興』の取り組み」が重要とした。紀伊は「将来のまちの姿を考える事前復興は、人口減少という危機への備えにもなる」と訴えた。高知も「被害を少しでも抑え、被災後も若い世代が住み続けたいと思える郷土づくりを進めたい」と強調した。
原発事故も現在進行形の課題だ。福島民友は「国や東電は新たな技術などに加え、過去の経験を生かし、廃炉作業などをどう着実に成し遂げるかが問われている」と指摘。大量の「除染土」も未解決だ。2045年3月までの最終処分が法律で決められているが、山陽は「期限内の最終処分をどのように目指すのか、具体的な手だてを示す必要がある」と述べた。指定廃棄物が1万㌧超ある栃木県の下野は「処分方法は決まっていない。未解決のままで問題を風化させることは許されない」とくぎを刺した。西日本は「流通している商品の安全性に問題はない。福島県産品を買い、復興支援の輪を広げたい」と呼び掛けた。
政府はエネルギー基本計画の改定案を閣議決定し、「可能な限り原発依存度を低減する」との表現を削除、原発を最大限活用する政策へ回帰した。これに関し朝日は「原発に依存しない社会をめざす。事故の経験という『出発点』を忘れてはならない」と強調。中国は「辛苦にさいなまれ続けている被災者の思いを受け止めた上での方針転換なのか」と疑問を呈した。
河北は「課題をたゆみなく発信し続けていくことが、私たちの務めである。誓いを新たにしたい」と宣言した。(審査室)